僕は1日の中で必ず『インプット』の時間を取っているのだが、最近はその中で『勉強法』ついての論文をよく読んでいる。
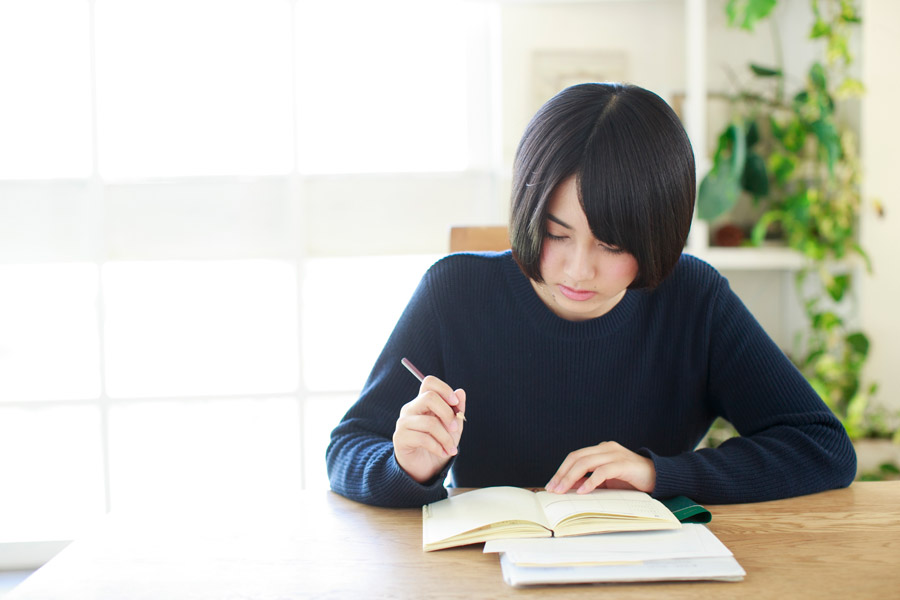
その中には、英語を教える側にとっても、学ぶ側にとっても、非常に有益な教えや結果が含まれている。これは是非ともシェアしたい。
ということで、出来る限り厳選し、ここにまとめてみる。
英語嫌いはいつから始まるのか?

大体初めて習う時や、中学校入学後は、英語の学習意欲は割と高い。(アルファベットや名詞の暗記が英語なのかという話はさておき)
だが、その意欲が急激に萎えるタイミングはどこなのか?というのはややアバウトな話である。
その時期が分かっていれば手が打ちやすい。それについて、興味深いデータが存在する。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/52/1/52_71/_pdf/-char/ja
すごく乱暴に言えば、中1の学習意欲の追跡調査のまとめだ。12月頃に、急激なそれの低下が、全体として見られる。
単元としては、『冠詞』『複数形』『三人称単数現在形』や、各種『疑問詞』がテスト問題などに登場してくる頃だ。
文法的なルールが急激に抽象化し、かつ複雑化するタイミングで、英語嫌いが爆増することがよくわかる。これは納得。
尚、この論文の最後の方には、以下の記述が載っている。
中学校1年生の英語学習における個別の教育的介入を検討する際には,1学期終了時における自己効力感に着目し,特に英語の勉強法についての補習授業等を行うことが,学習意欲の低減に歯止めをかける一助となろう。
―例えば、『音読学習』など、英語の効果的な学習を積む重要性を伝えることで、意欲が下がるのをある程度防げるという話っぽい。
確かに、大体2学期のタイミングから、『どうやって英語を勉強すればいいかわからない』という声が爆増するとも感じていた。
何をすればいいかわからないという迷いは、学習しようというやる気を思い切り削ぐ。声掛けとして、是非参考にしてみてほしい。
集団授業の学習意欲を高める、身も蓋もない話。
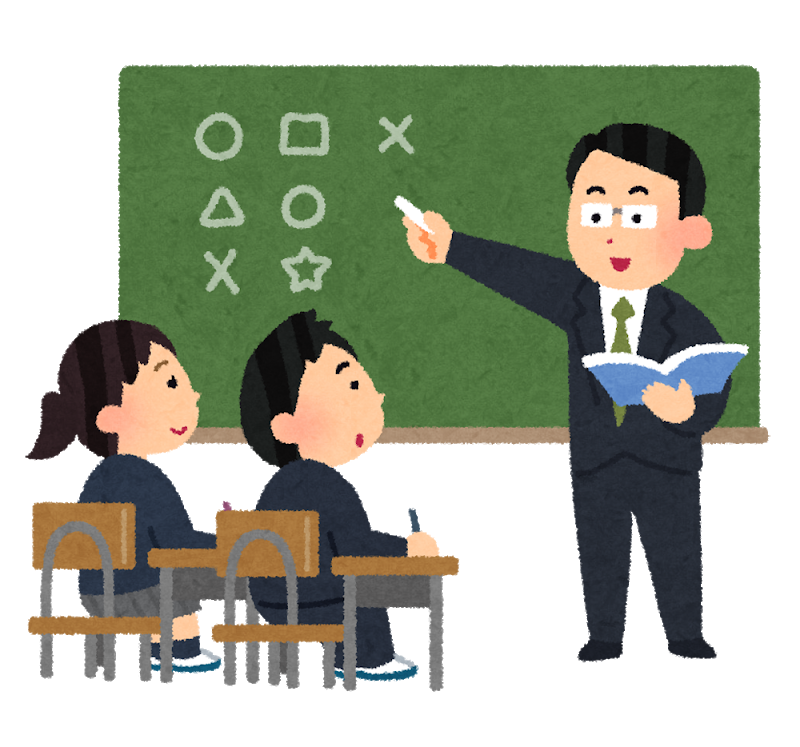
英語に限らず、集団クラスとなると、雰囲気作りに非常に頭を使わねばならない。悪い芽は摘み、良い芽は育てる。
だが、そんな『集団授業』の雰囲気を良くする方法とは、実際身も蓋もない話に落ち着くっぽい。
それは、『習熟度別クラス』の開設だ。曰く、母数はとても少ないものの、習熟度別クラスを受けた生徒の全員が肯定的解答をしているのだ。
また、『習熟度別クラスだったら良かった』という風にアンケートへ答えた生徒の声も紹介されている。
「もし習熟度別クラスがあれば、英語に対する不安などがもっと早くなくなっていたのではないかと思います。」
「少人数になり、発言などが増えるので、習熟度別は良い取り組みだと思います。」
「自分に合ったレベルの授業が受けられるので、あれば良かったと思います。」
「違うレベルの人がいたら、苦手な人は得意な人に笑われるとか、恥ずかしいとか思う人もいると考える。」
「クラス人数が少ないと先生のケアも届きやすいため、習熟度別は効果的だと考える。」
太字にしたところは、個人的に刺さった文言だ。
公立の学校だと、教員不足もありすぐすぐの実施は難しいだろうが、学習塾は大いに参考へしなければならないデータだと思う。
上のレベルは上のクラスへ、苦手ならば、ケアを密にできるクラスへ。シンプルだが、これが集団を円滑に運営するコツなのかもしれない。
『速読』の効果はどれくらい積めば出る?

英文読解に欠かせないスキルとして、『速読』と言うのがある。文法・単語・訳を丁寧につかみながら読む『精読』とは別の技術である。
だが、これまた英検を始めとする実用的な試験では必須のスキルなので、意識して鍛えねばならないものだ。
―では、一体どれくらい練習を積めば、目に見えて成果が出るのか?それを調べた論文があった。
すごく乱暴に、実験の内容をまとめる。
① 半年かけて、通常の英語とは別に、『速読』の授業を実施。
② 本文のレベルは、既出の文法・単語を考慮したもの。(恐らく学力より易しめ)
③ 『新聞をナナメ読みする感じ』という風に、求められる読み方は予め指示を出しておく。
④ 読了後は、付属のCDを使って『シャドウイング』や『朗読』を実施。
⑤ タイマーを用意しておき、終わった生徒は掛かった時間を毎度記録する。
―また、声掛けとして、かなり密な配慮をしていることも記載してあった。
さらに,速読後,内容理解のためのワークシートを通して、「時間内に読めているか」「現在より読むスピードを上げられるか」「WPM が伸びていても内容理解の正答率が著しく下がっていないか」等を意識させ,内容理解度と読む速度の適度なバランスが保たれるように助言を行い,他の生徒との競争や WPM を単に上げるだけが目標ではないと説明した。
※WPMはWords Per Minuteの略で、1分間に読んだり話したりできる単語数のこと。計算式は、文章の総単語数÷読むのに掛かった秒数×60である。
つまり、『目で文字を追っかけるだけ』にならないように配慮したうえで、その速読力の伸びを調査したという感じだ。
そして、結果は以下の通り。

なんと9回目には、1分間に読める単語量が100も増えていることが示唆されている。これは生徒に声掛けするのに使える!
(しかも生徒たち自身も、自分の英語の速読力の伸びしろを自覚していると、アンケートに記載されていた)
もちろん一概には言いづらいが、
『速読』の効果は、正しいやり方を徹底すると、『9回目くらい』でハッキリと出る!
と考えて良さげ。指導や声掛けの参考にされたし。
結局最強の英単語暗記法とは何なのか?

『大人』を対象とした効果的な英単語勉強法はあるけれど、それは児童に応用可能なのか?
・・・というのを調べた論文がある。↓
http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/10343/1/69-2-zinbun-03.pdf
長大な論文だったので、すごく思い切って要約すると・・・
小学生を対象としても、『分散学習』と『想起練習』は効果が高い!
という話だった。
まず、『分散学習』とは、『時間を空けて復習する』というものだ。例えば1日30分の勉強より、1日10分の勉強を3日に分けてやった方が効果が高いとされる。
実際にこの調査でも、いわゆる『詰め込み学習』グループと比べて、暗記量に差が出るかを調べているのだが・・。
ざっくり倍近くの差をつけて『分散学習』グループの勝ち、という結果が出ていた。
やはり間隔を空けて復習する方がベターである。
また、『想起練習』とは、何度もこのブログで書いている『思い出し』のことである。
簡単に言えば、例えば単語をただ目で追うのではなく、何とかして思い出そうという意識で取り組むことがそれ。
例えば、『覚えたけど意味が思い出せない』単語も、例文や先頭の数文字をヒントとして思い出そうとすれば、これも立派な想起である。
これまた、論文によれば、
『想起』で覚えたグループの暗記量は、そうでないグループより有意な差で上回っていた
という。有意が具体的にどれくらいかは不明だが、効果の高さは間違いなさげ。
しかも、時間を空けて再テストをして、知識の残り(≒長期記憶)を調べても、
『分散学習』と『想起学習』の完全勝利
だったというので面白い。単語の学習方法は、軽く結論が出ているとさえ思える。
授業のウォーミングアップに『単語の勉強』を取り入れる際の、良いヒントになるはずだ。
これは僕も取り入れる予定である。
終わりに。
色んな情報を手早く入手するためには、それが書物にまとまるのを待つのも一手ではあるものの、自分で取りに行く技を磨いた方が良いように感じる。
論文の読み方はぶっちゃけ我流も良いところなので、これからもその方法は練習し続ける所存だ。
僕の負担はぶっちゃけデカいのだが、有益な情報はこれからもこうしてシェアしていくつもりである。
それでは今日はこの辺で。