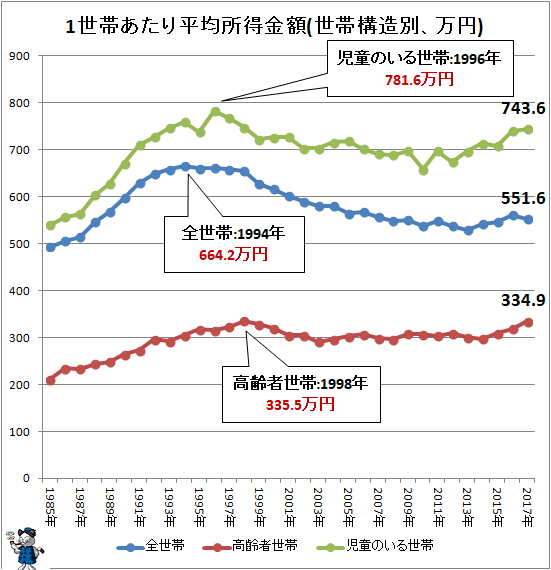ビジネスは本気で難しい。(同時にやりがいも覚えているけど)
大学で学んできた机上の経済学も、ぶっちゃけ凄まじい時代の変化も相まって、そのままでは全然活かせない印象だ。
その中でも特に、『集客』に頭を悩ませている。『マーケティング』とか小難しいことを学んでみたが、まだ概念が腑に落ちておらず、難儀している。
ということでこの記事は完全にチラ裏だ。僕の頭の中のカオスを書き殴り、自分の脳内の整理整頓用の記事として仕上げてみる。
役に立つか立たないかは、正直皆様の状況次第である。軽い気持ちでナナメ読みしていただければありがたし。
まずはよく言われる原因を考えてみる。
少子化の影響はどこまですさまじいのか?

結構多くの塾(特に地方)が、生徒数・問い合わせ数の減少に頭を抱えているという。
その原因として、いの一番に『少子化が進みまくってヤバイから!』みたいな話はよく聞く。
しかし、そういえば具体的にどこまでヤバいのかは、意外と知らない。ぼんやりと主観で解釈している方が多いのではなかろうか。
ということで調べてみた。すると、こんなグラフがすぐにヒットした。

確かに『高齢化率』の急激すぎる上昇は気になるが・・・。ここからだと、ハッキリ言って、僕らのターゲットたる『子どもの数』が全くピンとこない。
ということで更に調べてみると、こんな統計データを発見した。
統計トピックスNo.109 『我が国の子どもの数』
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/pdf/topics109.pdf
そこには、こんな血の気の引く要約が載っている。
≪全 国≫
Ⅰ-1 こどもの数は1553万人、37年連続の減少
Ⅰ-2 こどもの割合は12.3%、44年連続の低下
≪都道府県≫
Ⅱ-1 こどもの数は東京都のみで増加
―こう書かれると、少子化の凄まじさもひしひしと伝わってくる。また、読み進めると、色々なグラフが登場する。

まず、日本全国の子どもの数の推移。昭和25年に比べると、びっくりするほど数が減っている!!(平成初期と今を比べてもすごい)
また、都道府県別の資料もあった。

特に表3について、前年差の数の欄を見てほしい。
それが1桁だと少なく見えるが、例えば-3とはつまり-3000人である。
乱暴に言えば前年度から今年度にかけて、県内のマンモス校が3つ消えているも同然と考えると、やはりどうにもゾッとする。
さて。
これらの資料から、特に地方だと、縮小していくパイを各塾が取り合うレッドオーシャンになりつつある、というのが改めて分かる。
うーん、修羅の世界だ・・。のほほんとしていたら、確実に将来メシが食えなくなる!
―だが、『少子化』だけが、生徒数が減っていく理由ではないだろう。
冷静に考えれば、子どもは確かに減っているものの、まだまだ身の回りにはたくさんいる。囲い込めれば、それこそ経営は安泰な程に。
ということで、他にも原因の説明になりそうな生々しいデータを、もっと調べてまとめてみることにする。
各家庭の経済状況ってどうなってるの?

次に思い浮かぶ心当たりは、『各家庭の経済状況の悪化』である。教育費が食費より大切な家庭は、ぶっちゃけ存在しないだろう。
余裕が無ければ、特に塾なんかは、切り捨てられる対象にすぐリストアップされる。そんな印象がある。
過去何回か経済状況を理由に辞められたこともあるので、実際リアルはどうなのか、ちょっと調べてみる。
すると、めちゃ分かりにくいデータをグラフにしてくれている、大変ありがたいサイトを発見した。
それによれば、平均収入の推移は以下の通りになる。
おや?思ったより多いのだが。あれだけフィーバーしていた印象のバブル期よりも、今の方が上じゃないか。
(詳しい説明は割愛するが、これは額面通りに受け止めてOKとのこと。つまり、所得は30年前より今のがある。)
こうしてみると、経済状況の悪化も、根本の原因と考えづらい気がしてきた。
『生活が苦しい!』という声は多く聞く気がするが、それは単に『表現できる場ができたから』な気がする。
つまり、昔から『苦しい!』と感じる人は大勢いたが、それを超大多数に公表する方法が無かっただけで、今も昔も大差ない、と思うのだ。
うーん、では、多くの塾が『集客』に難儀する理由は、一体どこにあるのだろう?
すぐに考えがいく『少子化』『家計の悪化』も、こうして並べてみると、説得力が意外と弱い。
そこで次は、『生徒数がバカ多かった頃』と、『苦戦してる今』の間にある、最たる違いを基に考察していく。
それは、『インターネットの台頭』だ。以下、その続き。
『インターネット』は教育をどう変えた?
指導法のオープンソース化。

過去にここでもちょいと触れた寿司屋の修行ではないが、今の時代では、技術を秘密にすることで強みにするのは不可能に近い。
『この教え方はここでしか受けられないぞ!』というプレミアは、もはや死語だ。
何故かと言うと、その情報はネットを通じて簡単に手に入るからだ。或いは、参考書を使っても入手可能。
今や数多くの講師が、自分の指導をYoutubeなどで配信している。わざわざ塾に通い、指導を受ける意味が薄らいでいるのは、ぶっちゃけ否めない。
少子高齢化や経済状況の悪化よりも、教え方の希少性が薄れ、指導法がオープンソース化したところに、原因の1つがあるような気がする。
『知識』を蓄える意義の希薄化。

学校のテストで高得点を取ることは、とにかく暗記能力次第の側面が強い。(少なくとも僕が見た限り)
だが、知識を蓄えることの意味や意義は、ここ最近急速に薄れていると感じる。
何故かと言うと、ツール1つで、莫大な情報にたやすくアクセスできるからだ。覚えていなくても、調べれば出てくる。
漢字だって、書けずとも読めさえすれば、後はスマホやPCが変換してくれる。書き順が形骸化するのも、僕は時間の問題だと感じる。
―ということで、ここまで書いてきて思ったが、今までの集客が通じなくなったのは『ネットの台頭』が大きな原因っぽい。
今や経済モデルすら変化しつつある時代だ。僕らはどういった手を打っていけばいいのだろう。
―そのヒントになりそうな情報に思いめぐらせると、閃くこと、気づくことがあった。
それらを僕が実践できているかと言われれば、ハッキリと否だ。だが、意識としては非常に大切であることだと思う。
皆様にもすごく重要なヒントになると思うので、以下出来る限り言葉にして書いてみる。
これからの時代で『価値を持つ』ためには?
『何を』ではなく、『誰から』の時代へ。

あらゆる情報をいとも容易く入手できるようになった今、『情報そのもの』が価値を持つことは稀になってきた。
さっきも書いたが、『あの塾は独自の指導法で~』みたいな文言は、将来的に確実に通用しなくなってくる。少なくとも、その効果は薄れていく。
では、他に何で勝負すれば良いのか?
それは、どうやら『人柄』であるらしい。

誠実さや優しさなど、一周回ってそういった『人として』の価値が高まる時代になってきているのだという。
例を挙げる。料理人が二人いて、どちらも料理の腕は同じだとする。片や不愛想、片やニコニコとノリがいい。どちらのサービスをアナタは受けたいか?
その答えが、上記の事柄の理由でもある。
今や教え方は誰でも手に入れられるようになったからこそ、それを『誰がどう』伝えるかが要になってきているのだ。超納得。
―それを考えると、色々と心当たりがある。
僕らはハッキリと中小なのだが、大手の塾から移ってくる生徒がたまにいる。理由を聞いてみると、割と以下のどれかにマッチする。
『先生が全く合わない』『面談で一切褒められない』『欠点ばっかり並びたてられる』等々・・・。
つまり、成績のアップダウンではなく、そこの人との関係性がかなりデカいファクターなのだ。
大手だからとか、謎に高尚なプロフィールを持ってるからとかで変に踏ん反り返ると、一発アウトの時代になったということか。
これは怖くも、同時に嬉しい話だ。なぜか?それは次項に述べる。
『職人』は要らない。

僕は、先ほど述べたみたいな『人柄』が評価される時代を、ハッキリと歓迎する。
理由は簡単。それは、いわゆる職人(カリスマ)と対等に戦える土俵が新たに出来ることに他ならないからだ。
例えば、超絶わかりやすい授業をするが、生徒の自尊心をへし折るような言葉遣いをする講師を考えてみよう。
『こんなのもわからないとか甘すぎ』『絶対落ちるからな』等々。聞いていて吐き気がする。
昔ならば指導力をウリに十分稼げたはずだが、今はそうもいかない。生徒の自己肯定感を大切にし、評価する講師の方が、ビジネスで勝てるかもしれないのだ。
つまり、この辺りの要素を如何に高め、生徒やご家庭にどう伝達するかがカギになりそうだ。僕の目指すものがだんだんはっきりしてきたぞ。
―ということで、より具体的な施策について、次に思いめぐらせてみよう。
これからの時代に必要な『塾』の在り方とは?
まず、生徒の自尊心をへし折らない!

当たり前と言えばそうなのだが、生徒の自尊心をへし折らない校風を徹底するだけで、特に大手と差別化ができると感じる。
不思議な話だが、大手ほど、どこか生徒を不安や恐怖をモチベに動かすような印象がある。これは僕の知る限り、だが。
実際、怒気をはらんだ叱責や個人攻撃、強めの罰や夥しい宿題などは、確かに生徒を動かせる。
ただしその対価として、とんでもない量の何かを失うことにはなるけれど。
それでも、今までは培ってきたネームバリューや、入らない他塾の情報が相まって、生徒が離れなかったのだと思う。
もしかしたら、『厳しい指導で俺も伸びたからだ!』みたいな価値観があるのかもしれない。だとしたら有難迷惑だ。
でだ。たまに僕のところにも、他塾でメタメタにされた生徒がやってくると先述したが・・・。
大半、自尊心が恐ろしいほど低いのだ。テストで結果を出しても喜ばない。それどころか、こんな点では情けないと、自分の結果を否定することもある。
こんな状況にまで追い込むとか、どういう指導をしているのだろう?と僕は純粋に首をかしげる。
逆に、生徒を大切に扱うと評判の塾から移ってくることは、ほとんど(というか僕の知る限り全く)無い。
僕の狭い情報網で恐縮だが、『講師の人柄』は塾の集客と維持において、重要な要素とみて間違いなさげである。
―繰り返すが、もはや『何を教わるか』の内容は、ネットなり参考書なりで簡単に得られる。上手い授業ができるからと言って、威張ることは無理。
その内化けの皮が剥がれれば、心を傷つけられてまで一つの塾に固執する生徒は激減してくるはずである。
そうして逃げられる側にならないためにも、まずは生徒の自尊心や自己重要感を絶対に傷つけない、そして満たすような声掛けをするべきだ。
昨今、SNSの普及もあり、精神的に疲れている子も多いと聞く。それを『甘えるな!』と突き放すのは論外だ。
まずはそこを受け止めてあげることを、繰り返すが校舎で徹底した方がいい。今の時代を考えると、どうしてもそう思う。
旧来の学習スタイルにこだわらない。

ネットで少しサーフィンしても、『裏付けのある勉強法』は大量にヒットする。
これをガン無視し、効果ナシと否定された学習法に固執すれば、成績が上がらないのも当然だろう。
だからこそ、僕は『勉強法』について、とぉにかく口やかましく『効果の無いもの』を否定し続けている。
ちなみに現在は、『ながら勉強』と『ノートに写すだけ勉強』に絞り、まずは撲滅を目指している。
それを徹底するため自習室にもテコ入れを始めたところだ。
とあるYoutuberも言っていたが、『生き残るのは強いものではなく、変化できるもの』とはその通りだと思う。
旧来の学習スタイルや指導法も、捨てるに値するデータが揃ったら、どんどんと捨てる。そして、新しいそれらに変える。
今の時代、そういう姿勢の方が、結果勝てるのだろうと思っている。
『分散化・多様化』を目指す。

今や、何かのコンテンツを始めるにあたり、本当に初期投資のコストが減ってきた。これはインターネットの正の側面であろう。
例えば、かつては師弟制で完全に閉鎖的だった『そろばん』の使い方も、今やネットで簡単に見れる。
となれば、今は『門戸を広げる』のがとてつもなく簡単になっているので、過去とは比べ物にならないくらい多様な塾も作れるということだ。
例えば、書道も、各種検定も、基本的な数学の計算も、『映像』というコンテンツの権利を買えば手軽に導入ができるそうだ。
とにかく取っ掛かりを広く持っておくことで、色んなニーズに応えつつ、接触を増やす。
これもまた、新しい塾の形としてアリかもしれない。
逆に、『極端なニッチ』を目指すのもアリ。

インターネットの台頭であらゆる情報が有機的に繋がった今、実は面白いものが『価値』を持つようになってきているという。
それは、『極端さ』だ。
僕の好きなバーに、『SABAR』というのがある。ここは見事に、全メニューが『サバ』である。
店内のレイアウトもサバにまつわるもので徹底されており、たまにはアジを・・とかは絶対に無い。
だが、めちゃくちゃに繁盛している。実際に僕もハマっており、年に4回は行っているほどだ。
ここからもわかる通り、分散化や多様化も確かにカギではあるが、逆に『何か1つのテーマ』に超絶特化するのも戦略としてアリである。
テストで全科目が80点あるヤツだけが評価されていた時代から、他が0点でも何かが500点あるようなヤツも認められる時代になったっぽい。
あらゆる塾が手広さを武器にしているなら、逆に徹底して絞るのもアリかもしれない。『数学は全部お任せ!』みたいな具合だろうか。
自分が熱狂できるもので、かつ塾の仕事としてズレていないもの。そういうのがある方は、分散するより集中する方が良いのかもしれない。
授業は何を目指すべきか。

最近超話題の塾に、『探求学舎』と言うところがある。
簡単に言えば、子ども達の『もっと知りたい!学びたい!』という好奇心に火をつけることに特化した塾である。
見学に行った人の皆すべてが、その圧巻の授業(?)に感動し、キラキラした目で帰ってくるのが印象的だ。
僕自身は生で見たわけじゃないが、僕個人としても、目指す授業のゴールはここだなぁと強く感じているところだ。
どれだけ口やかましく言おうとも、自分から学ばない子を成長させるのは難しい。
体罰や叱責が通じなくなってきたならなおさらだ。『いいからやれ!』では動かない。
強制的な課題も罰もなく、自然とやってみようかな・・と思ってもらえるような授業。内発的動機で学べる子は、誰よりも強い。
僕は仕事を始めて5年目だが、今までのスタイル全てを捨ててでも、ここに行きつきたいと思っている。
終わりに。
ということで結局最初に書いた通り、全然取り留めが無い記事になってしまった。
無理矢理要約すると、僕の言いたいことは以下の通り。
① 『少子化』や『経済状況の悪化』は、集客に難儀する理由としてちょい弱い。
② 『教えるのが上手』ってだけではもうメシは食えない。
③ これからは『人柄』と、新しい『コンテンツ』が要?
という具合。もちろん、例えば家族構成の変化とか、色んな原因はチラホラ浮かぶが・・・。今日はこの辺に留めておく。
最後に、『信用がこの時代の重要なファクターだ!』と僕が思うようになった(というか気付けた)きっかけの良著を載せておく。
これからはどんな人が求められるのか気になる方は、ぜひご一読いただきたし。
では、長文にも関わらず、お読みいただきありがとうございました。