増量は順調ですが、ずっと続く満腹感が苦しい中元です。
はい。次の洋書を何にしようか10分以上考えた。例えばハプスブルク家の歴史とか、メディチ家の遺骨調査レポートとか、今ハマっているYouTube関連の本を考えたが・・。
どれもしっくりこなかったので、結局サイモン・シンの作品を読むことにした。同じくドキュメンタリーのジャンルから、【BIGBANG】である。(K-POP関係ないよ)

こちらも和訳版が出ており、そちらのタイトルは【宇宙創成】というものになっている。(これももちろん神懸かり的に面白い!)
そしてざっと読む感じ、イラストもしっかり省略されずに載っているようで一安心。そういえば、フェルマーの方は、数学者の写真が全部消されていたのでマジ驚いた。
ってことでワクワクしながら、新しい洋書を読み始めようではないか。以下、その日々の感想文である。
- 1月21日(金) 巨人が創った世界
- 1月22日(土) 巨人が創った世界Anywhere
- 1月23日(日) 科学の始まり
- 1月24日(月) 美しさとは
- 1月25日(火) 地球の大きさを計る
- 1月26日(水) 中休み
- 1月27日(木) 科学と実利
- 1月28日(金) 見た目か真実か
- 1月29日(土) 見た目か真実か2
- 1月30日(日) 見た目か真実か3
1月21日(金) 巨人が創った世界

神々の世界アスガルドと9つの世界 北欧神話の世界ガイド - パンタポルタ
現在広く受け入れられている?ビッグバンモデルが完成する前は、教会が考える天動説が広く普及していたとある。
では、その前はどうだったのか?確かにそこにあるのに、絶対に手が届かないところへ、人々はどんな想像を働かせ、どんな説明を作ったのか。
不思議なことに、あちこちで、超巨人が世界を創ったという似た伝説が存在することから、同じく人智を超えた存在が太古に存在したと仮定されたらしい。
場所が違えどこの辺が似ているのって、偶然だろうがスピリチュアルなことを感じさせられる。なんかロマンだなと、アホなことを考えてしまった。
1月22日(土) 巨人が創った世界Anywhere

神々の世界アスガルドと9つの世界 北欧神話の世界ガイド - パンタポルタ
今日も早出のため、ほぼ読めず。2ページほど読んでみたが、巨人が世界を創った話の続きであった。共通点はまだまだ続くらしい。
説明がつかないけど確実に存在する、圧倒的な存在。そういえば僕は星のカービィが好きなのだが、特に宇宙に飛び出すステージが好きだったなぁ。
なんか懐かしいことも思い出せた。だから宇宙は楽しいぜ。
1月23日(日) 科学の始まり

超自然的な存在で、目の前の事象の理屈を説明付けるのは、最も科学的から遠い話の一つらしい。例えば落雷は雷神のせいってのは、実は何の説明にもなってない。
初めて神の存在を使用せずに宇宙を説明しようとしたのは、古代ギリシャの哲学者だったとのことだ。
曰く、地球の周りは黒い天幕で覆われており、その向こうでは業火が燃え滾っている。
その天幕に空いた穴こそが、実は太陽の正体なのだ、という風に。
もちろん現代から思えば荒唐無稽なのだが、超自然的存在を考えずに説明を試みたという点では非常に画期的なのだという。
そしてその後、万物を「数」で説明しようという動きが登場する。そう、フェルマーの最終定理にも登場した、ピタゴラスがその発端である。
神を用いず、観測と数学で事象を説明する。今思えば当たり前のこのプロセスも、紆余曲折の結果だと思うと、なるほど心が熱くなる感覚がある。
壮大な話って、やっぱ面白いですな!!
1月24日(月) 美しさとは

誰が言ったか忘れたが、自然現象を説明する公式なり定理なりは、シンプルであればあるほど美しく、また正しいという考えがある。
そして現実世界を説明するそれらを作った後は、それで未来の予測を行い、整合することが確認されてはじめて、世に受け入れられるのだという。
これらの武器とプロセスを使い、なんと算数の知識と観測データだけで、地球のサイズを計算しようとする人が、古代ギリシャの時代には、出てきていたのだという。
規模のデカイ話だぜ。ただ、ここで時間が来たので、こっから先はお楽しみである。
1月25日(火) 地球の大きさを計る

数学が苦手過ぎて説明しきれないのだが、夏至のときに井戸の底まで太陽光が届くことを利用し、扇形の弧の長さを出す的な計算で、地球のサイズを出した人がいる。
それは、エラトステネスだ。
こうやって一度地球のサイズを概算してしまえば、月のサイズもわかるし、月のサイズがわかれば、月までの距離もわかるというわけ。
もちろん用いた指標が「歩幅」といった感じで厳密性を欠くところもあるが、問題はそこじゃなく、数学と推論と実験で答えを出せたという点がすごいと思う。
ちょっと図形関連の数学、勉強し直そうかな。
1月26日(水) 中休み
食中毒疑惑のレベルで体調が悪いため読めず。皆様もお大事に・・。
1月27日(木) 科学と実利

科学者と技術者の違いが面白かった。科学者とは、好奇心に突き動かされて物事の真理を突き止めようとする人たちのことであるという。
一方技術者とは、物事を便利にすることを目的として、様々な道具を生み出す人たちのことだとあった。
前者は「なぜ?」を原動力にして、後者は「便利さ」「有用性」がモチベーションになるのだという。つまり、似て非なるものなのだ。
科学者が発見したことを日常生活に取り入れるのが技術者。そういう風に、役割が違うものと考えてもいいかもしれない。
同様に、哲学者と天文学者の違いも書かれていたが・・。読み切る前に時間切れ。体調もまだ優れないので、無理はしないでおきますわい。
1月28日(金) 見た目か真実か
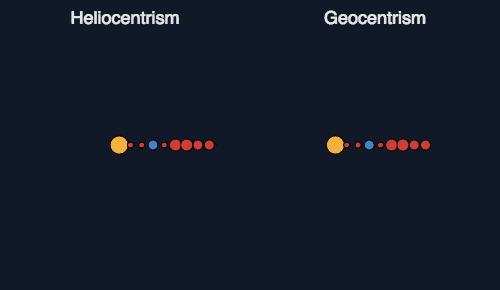
ある程度読んでいくと、天動説VS地動説の走りみたいな話が出てきた。ぶっちゃけ、地球上に住む自分たちにとってみれば、地球が"周る側"なのは想像し辛いだろう。
だからこそ、前提がそれになることに、何の不思議もないわけで。そういうわけで、それを説明するようなモデルが生まれてくる。
それが天動説だ。しかし、天動説を準拠にすると、上記のGifアニメの右側みたく、非常に不可解で複雑怪奇な動きを求めないと、説明にならないのだ。
科学はシンプルな方が正解という理念には思い切り反している。
見た目か、それとも真実か。何がどうなって最終的に地動説に行きつくのか、楽しみに読みたいと思う。
1月29日(土) 見た目か真実か2

地動説が受け入れられなかった理由も、実はごもっともという感じがする。
地球が動いているなら、常に爆風が吹いていなければおかしい!ものが太陽に落ちていかないのがおかしい!星の位置が変わって見えないとおかしい!はい論破!
的な。実はその1つ1つに、今は一応、説明が存在する。
地球は動いている。なのに爆風が感知できないのは、大気ごと地球と一緒に移動しているためである。
ものが太陽に落ちない理由は、地球に重力が働いているから。
星のみえる位置は、時期によって厳密には変わっている。ただしあまりにもそれは小さいので、肉眼では感知できないってこと。
みたいな。
こうして、大昔はそう考えていたんだよという風に遠い世界を見るような思考ができるのも、科学が進歩してきた恩恵と思うと、胸がちーと、熱くなる。
もちろん、そもそも疑問を宇宙に差しはさんだ人たちも、めちゃすごいんですけどね。
1月30日(日) 見た目か真実か3

火星の意味不明な軌道や各種惑星のふらふらっとした位置の変化と天動説に、どう折り合いをつけるべきか?
古代の人が数世紀も悩みに悩みぬいて、遂に出した結論が、周転円とのことだった。
読んでいると頭が痛くなるのだが、つまり地球の周りを、それぞれの惑星が特色ある円を描きながらぐるぐる回っているという感じらしい。
結果出来上がったモデルは異常なまでに難解であり、それでも説明できない部分は少なからず残っていた。しかし、実際を説明できるから、良いか、と。
ということで、この辺の論争や真偽の追及は、ボチボチ次の世代に引き継がれそうという展開であった。
ってことで今週はこの辺で。
