不安の話が終わり、依存へと移った。メンタルヘルスという発展途上の学問ゆえに誤解や嘲笑が発生しがちな分野の知識が、体系的に身に着いてきつつある。
仏教哲学を学び、発達障害の例を学び、あらゆるサプリやハーブを試してきた僕だったが、ここにきて改めて幹に該当する知識を得ることは、すごく良い学習となっている。
jukukoshinohibi.hatenadiary.com
頭の中を切り捌いても、ぶにぶにしたヘンな臓器があるだけだ。脳をスライスしても、その人の思考を理解することはできない。アインシュタインは量産できないのだ。
僕の脳内を共有することも困難なのに、まして人のそれを汲み取るとなると、これは永遠に達成不可能ではないかと思えてくる。
言葉が生まれ、文学が誕生して数千年のときが流れているとされるが、まだ人類はその辺を改善しつつある途上、しかも前半戦にまだ居るのではないかと感じる。
だからこそ、学びの手は止めずに在ろうと思う。では以下、本題である。
- 5月20日(月) 本当の意味での”依存”。
- 5月21日(火) 「だらしないのねぇ」という刃を突き立てるという残忍な行為。
- 5月22日(水) 真綿で首を絞められている最中に気付けるか?
- 5月23日(木) 僕もまた被献体なりや?
- 5月24日(金) 適応という不可逆な呪い。
- 5月25日(土) 適応という不可逆な呪い。
- 5月26日(日) 奪われゆく楽しみ。
5月20日(月) 本当の意味での”依存”。
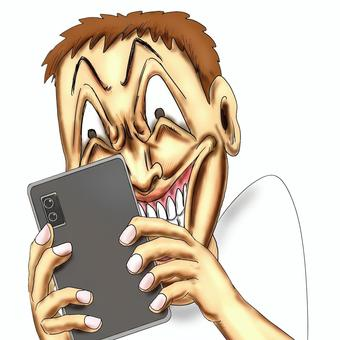
依存症の例を見ていると、その病的な重篤さがよくわかる。スマホ依存症なんて言葉は、やはりその言葉本来の意味と比較すると、てんで合ってないと感じる。
例えば、日増しに量が増えて、止めたら悪寒や苛立ちが生じ、それを探すことに1日の大半を捧げる。
それによって得られる満足感は減り続けているのに、摂取量ばかりが増幅し続け、しかも治療無しには意思の力で減ることもない。依存症とはこの次元だ。
そう考えると、モンスターハンターに熱中していたあの頃も、酒を毎晩飲みまくる今も、依存症というよりただハマっているだけなのだろう。
だからといって俺は依存症にならないと思い上がるつもりもないが、人は簡単には病気にならないのだなと、再確認できた心持ちである。
5月21日(火) 「だらしないのねぇ」という刃を突き立てるという残忍な行為。

それを使っても幸福になる訳ではなく、それを使っていないと辛くて仕方がない。依存症の例はやはり、とても怖い。
詳しく調べた訳ではないが、身近にあり、すぐ手に取れて、何かしらの報酬が即時得られるシステム。これらが依存症を誘発する代表格らしい。
すなわち、酒やタバコ、SNSなどによる承認といったものが、依存症を生み得る代表格なのだという。
端から見れば、依存症当事者というのは、そういったものの奴隷になっているように見えて、無知からの小言を言いそうにはなる。
ただ、思いに反して身体が動かない、意思が暴走するといったことは僕にも経験がある。だからこそ、利いた風な口は叩くまいと、気が引き締まる。
5月22日(水) 真綿で首を絞められている最中に気付けるか?

酒やドラッグによって人は多幸感を得られるというが、ではその多幸感の正体とは何なのか。
それを説明することはとてつもなく困難なほど、薬物の成分とそれによる脳機能への影響は、極めて複雑らしい。
あれをすればこれが起きる、というシンプルな話に落ち着く方が希で、バタフライ効果のような出来事があちこちで同時に起きるようなのだ。
【熟達論】にも書かれているが、構造の一部分を、他への影響なく取り出して鍛えるのは不可能という話に似ている。
酒を止めれば健康になるとか、そんな雑な話ではないんだなと、なんか覚めた自分がいる。
5月23日(木) 僕もまた被献体なりや?

僕が正直、脳機能で一番不思議だと思うのは、【報酬系】の存在である。
何らかの(主に生存において)好ましいことを行うと、脳は快楽物質を分泌し、その行動を取りやすくする。
遺伝的アルゴリズムの設計にも流用されるくらい、シンプルだが効果的なシステムなんだろうと思う。
ではなぜ、酒の飲み過ぎみたいな死を早める行為にも【報酬系】は働くのだろうか。一方、勉強のような必要なことに【報酬系】が働きづらいのはなぜなのだろうか。
多分だが、あちこちで指摘されているように、脳のアップデートが原始時代からまだ完了してないと、それだけなんだろうなと思っている。
5月24日(金) 適応という不可逆な呪い。

脳は大抵の状況に適応することができるが、この「適応」とは、素晴らしいシステムに見えて厄介な側面も持っている。その例として、すごくわかりやすい話があった。
ある小さな町を想像する。住人もそこまで多くないコミュニティで、ある種牧歌的な生活を送れる、閉鎖的ではあるが快適な暮らしができる場所を想像してほしい。
そんな町に突如として、巨大なスタジアムが建設されたとする。しかもそれは、一晩で突然、元々その場にあったはずの公会堂などと置き換わる形で、登場したのだ。
すると、そこで行われる試合やコンサートを目的に、多くの人が町の外からやってくるようになる。小さなコミュニティだったところに、外部資本が大量に流れ込むのだ。
当然それに合わせて、町の施設も置き換えられていく。ホテルが増え、飲食店も増え、畑などもそれらに転用されていき、観光業特化のところへ、”適応していく”のだ。
―しかしそんなスタジアムが、再び突如として消え去り、また公会堂に置き換わったとする。そうなればもう、ホテルや飲食店が乱立した場所は、その状況にそぐわない。
結果、最適化された状態・環境が変化した瞬間から、歪が生まれるようになり、町に多大なダメージをもたらすことになる。
このスタジアムを、例えばアルコールやドラッグの常用に置き換えると、依存症の構図そのものになる。なんと自然発生的に起こっていくのだろうか。
とにかく不思議で、どうにも怖い話だと、僕は思う。
5月25日(土) 適応という不可逆な呪い。

ドラッグによるハイは、「破綻した約束」だという。これは僕自身が教科書等で見知っていたことと一致する。
脳は全てに適応する。最初の快楽にさえ、脳は馴れていき、同じ刺激で同じ興奮を得られなくなるのだ。
それは身体も同じだ。例えば筋トレも、同じトレーニングを続けていたら、成長は止まる。刺激が変わらないためだ。
馴れとは頼もしくも思うが、ある意味とても恐ろしい。そのことがすごくよくわかる話である。
5月26日(日) 奪われゆく楽しみ。
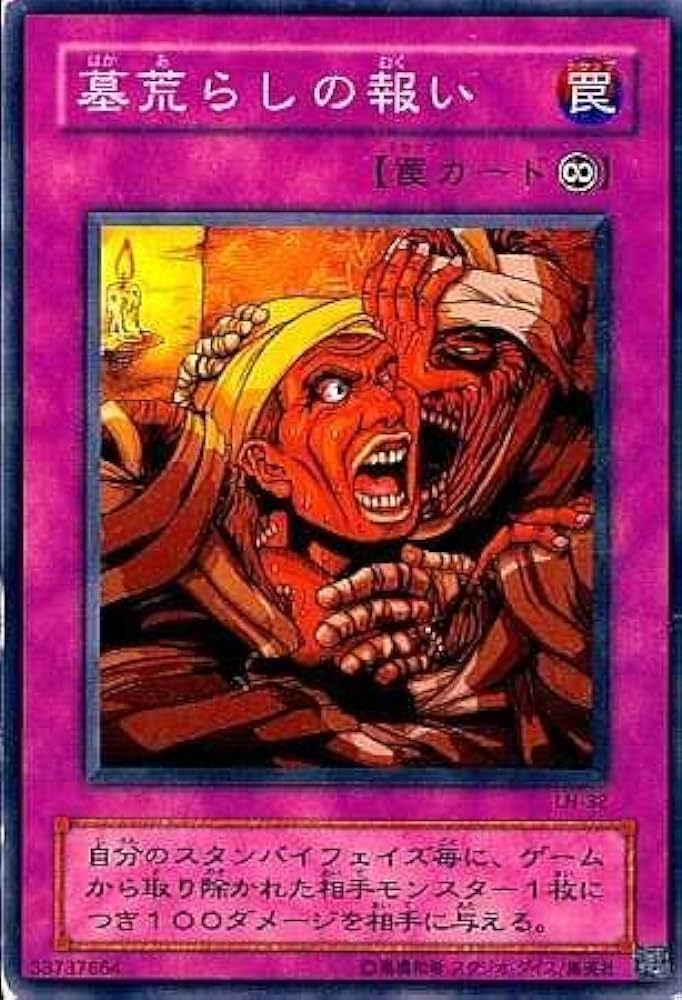
報酬系が鈍くなるということは、依存を加速させるだけじゃなく、その他の娯楽の楽しさを奪うことも意味する。
例えば僕は今、釣り・キャンプ・散歩・読書なんかをしていると、心が落ち着く感じがあり、素直に楽しいと感じられている。
だが依存が加速して、それこそ酒やドラッグでも快感を得られにくくなると、そういったささやかな幸せは無に等しくなってしまうのだ。
依存症が根深い理由が段々納得できてきた。それ自体が非常に多くのモノを奪い去ってしまうからだ。他の物を使って気を紛らわせるとか、そんな次元じゃないのだ。
お酒、控えよう。不思議とそう、思った。
では今週はこの辺で。